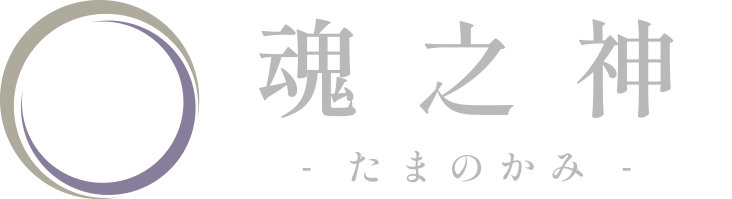お守りの種類と正しい扱い方|複数持ちはOK?納め方・神道と仏教の違い
日常の中でふと目にする「お守り」。
しかし、どんな種類があり、どう扱えばいいのか、意外と知らない人も多いのではないでしょうか?
この記事では、神社・お寺それぞれのお守りの意味や役割、神道的な視点でのお守りの扱い方を分かりやすく丁寧に解説します。
お守りとは何か?|起源と基本的な役割
お守りは「神仏のご加護を受けるための媒介」として、日本古来から授与されてきた霊的アイテムです。
もともとは神社や寺院において、神様や仏様の分霊・ご神徳を宿すものとして授けられたのが起源。古くは「御札(おふだ)」として家に祀ることが主流でしたが、江戸時代以降、携帯しやすい「お守り袋」型が一般的になりました。
神社のお守りの種類とその意味
神社で授与されるお守りには、明確な目的や願意があります。主な種類は以下の通り:
| お守りの種類 | 意味・目的 |
|---|---|
| 厄除け守り | 災いや不運を遠ざける |
| 縁結び守り | 良縁や人とのつながりを導く |
| 学業守り | 勉学や試験合格への加護 |
| 交通安全守り | 運転中の安全・事故除け |
| 金運守り | 金運上昇、事業繁栄など |
| 健康守り | 病気平癒や心身の健康 |
神道の考え方では、神様は八百万(やおよろず)存在し、それぞれの得意分野に応じて加護を授けてくださいます。
たとえば、金運で有名な「金蛇水神社」では、金蛇大神(巳神)が商売繁盛・金運上昇のご利益で知られています。
お寺の護符・お守りとは?神社との違い
お寺で授与されるお守りは、仏様や菩薩の慈悲や功徳を身に受けるもの。代表的なのは以下の通りです:
- 不動明王の「災難除け」
- 観音菩薩の「病気平癒」「子授け」
- 地蔵菩薩の「子どもの守護」
神社=神の加護、お寺=仏の功徳という点で、役割は異なりますが、どちらも「祈りの形」として大切な存在です。
お守りの正しい扱い方【神道的視点から】
身につけ方・持ち方
- 肌身離さず持つ(ポケット、カバン、財布など)
- 車用なら車内に設置(ダッシュボードやミラー)
- 家内安全や仕事運は職場・自宅の目立たない清潔な場所に安置
複数持ってもよいの?
大丈夫です。神道では「神様同士が喧嘩する」という考え方はありません。
ただし、ご縁をいただいた神社・仏閣を尊重する気持ちが大切です。
他人からのお守りはどうする?
気持ちを受け取ることが大切。感謝して受け取りましょう。気になる場合は、自分が信頼する神社に一緒に納めるのもよいです。
古くなったお守りは?
→年始や節分、または授与から約1年を目安に、授かった神社や近隣の神社で「お焚き上げ」に納めましょう。
神道的には「モノにも魂が宿る」と考えられています。だからこそ、ゴミとして捨てるのではなく、感謝を込めて納めることが大切なのです。
お守りを通じて、神様と心をつなぐ
神道におけるお守りは、「願いを叶えるアイテム」というよりも、神様と自分をつなぐ小さな依り代(よりしろ)という意味合いが強いです。
持つことで「神様と常に一緒にいる」という意識が生まれ、自らの行動や心も整いやすくなります。
日々の暮らしに神聖な意識を取り入れる
お守りは、ただの縁起物ではありません。
神仏とのご縁をいただき、心の拠り所となる神聖な存在です。
それを理解し、大切に扱うことで、「日常が少しずつ整い、心に静けさが宿る」。
そんな体験を、ぜひ皆さんにもしていただきたいと願っています。